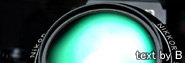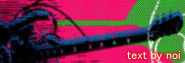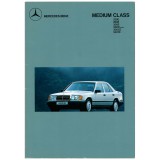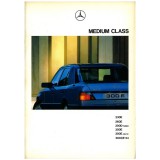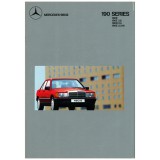国産車 低燃費に「?」
朝日新聞1月22日付け夕刊トップ記事のタイトルだが、カタログ表記と実燃費は別物と随分前から言われており、少しでも実燃費に近い表示をしましょうと、記憶する限り10モード、10.15モードと変わってきている。でも、まだかけ離れた数値であると言うユーザの指摘を受け、国交省は新たに実走行により近いとされるJC08モードを採用し、今年4月以降は表記が変わるとのこと。

朝日新聞1月22日付け夕刊の大見出し、国産車 低燃費に「?」カタログ表記の燃費に対し実燃費の達成率が示されていました。 「建て前と本音」?
2010年3月発表のe燃費による実燃費のランキングは、プリウスが21.7km/ℓで1位、アメリカの基準でも1位となる。だがカタログ値は、皆さんご存じの38km/ℓとなっておりカタログ値の達成率は57%で、言っていることの半分チョイでしかない。2位3位のホンダもそれぞれ64%、60%の達成率ユーザにとってほとんど意味のない数値が並ぶことが問題だ。
38km/ℓは国が定めたルールの中でたたき出した数値で決してウソではないのだろうが、仮にプリウスは22km/ℓとカタログ表記しても、現在世界のトップランキングであることは事実。建て前をあまりにも追いすぎて本音とのギャップがありすぎ、日本的なのかなぁ?
なぜ専用ドライバーなのか?
記事によれば、メーカーは良い結果を出すためにコンピューターのプログラムを調整していることと専用テストドライバーが運転するからと国交省関係者は分析する。と書かれていた。(答えです)
対し輸入車は1位フィアット500の16.8km/ℓで達成率は88%、2位3位のパンダ、ゴルフは92%、87%となる。海外のメーカーは自国で有利なようにプログラムを組むのだが、選任ドライバーは用意しないので実際の走行と大きな差は生じないとされる。これを読むと燃費はドライバーの腕?に掛かっている。という結論ですね。(乗り手で変わるのが燃費。あたりまえですが)国連では13年を目標に国際的な統一基準を作る動きが出始めたとのことです。
そもそもクルマも道具の一種とすれば、誰が使っても(乗っても)ほとんど同じような結果が出なければおかしいでしょう。何で専用ドライバーなの!
ところで18年前の古いW124 280Eの燃費は?
10.15モードよりもっと現実離れしていた10モード表示の時代です。
カタログ値の10モード燃費6.9km/ℓに対し平均6.28km/ℓで達成率は91%(10モード時代でもこの達成率ですしここが肝心です。)となります。その中で最低は4.06km/ℓ最高8.99km/ℓでした。 2002年にSSBSのブレーキ整備施行後のデータは平均7.27km/ℓで達成率は105%となり、最低5.06km/ℓ最高が12.94km/ℓを記録し確実に燃費は改善されました。(燃費はSSBSの整備の本命ではなく副産物なのです。)燃費計測を再開した2007年(1998~2006年は燃費未計測)だけで見ると年間平均燃費は7.96km/ℓとなり26%の燃費向上が確認されたのでした。
同じ個体で同じドライバーが運転しても4.06km/ℓから12.94km/ℓもの幅がある燃費、乗る環境や状況で変化することは常識ですが、それにしても国産車のカタログ値と実燃費の達成率が57~64%とは・・・!
燃費とは・・・。
誰でも良いに越したことはない。M/Tで2、3速を多用すれば悪化するし、A/Tでやたらキックダウンさせるように走っても悪化します。でも運転していて楽しい走りがありますね。そしてクルマの調子を見るバロメーターであったり・・・。燃費、命ならプリウスや軽カーまたは自転車の選択肢があります。
しかし、業務用なら徹底的に追って欲しい燃費。トラックの燃費がリッター50キロなんてなってくれればキット商品の売値は下がりますよね。趣味の場合は自由です。でもリッター2キロの車に乗ったら、他のことで節約して低炭素社会に貢献しなくてはいけません。(お利口さんは)