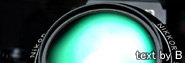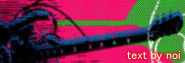アメリカで流行していたサンドバギーにヒントを得て作られたのがフェローバギー。フェローのコンポーネンツを活用し、本場のメイヤーズマンクスとは一線を画すFRPボディを換装したクルマ。もちろん当時の軽自動車規格だからエンジンは360ccのわずか26馬力にすぎないが、車重は440kgに抑えられ、軽快なフットワークを可能とした。
| |

D-BONE
2003年の東京モーターショーに参考出品された「D-BONE」。フェローバギーのスピリッツが生きる比較的最近の例。もちろん当時と比べれば何から何まで洗練されていることは間違いない。大切なことはダイハツが今でも遊び心を持ち続けていることだ。実際には同時期に参考出品された「コペン」が、実際に市販の陽の目を見ている。 |
ダイハツという会社は1907年(明治40年)に「発動機製造(株)」という名称で創立され、1951年(昭和26年)、現在のダイハツ工業(株)に改称されて今日に至っている。
1967年(昭和42年)にトヨタとの業務提携を始めてからは、トヨタ系列の会社のように思われているが、その遊び心のスピリッツはスモールカー(軽自動車)に強い企業の中にあっても、今なお脈々と生きているものと信じるし、信じたい。
その象徴的なクルマが1970年(昭和45年)、100台限定で発売された「フェローバギー」だ。
この遊び心満載のクルマに至る前にも、ダイハツには独特の洒落っ気というものがあった。1957年(昭和32年)、一世を風靡した、働くクルマ「ミゼット」にもその感性は宿っていたし、1965年(昭和40年)に発表された「コンパーノ・スパイダー」こそ、遊び心、冒険心、洒落っ気満載で、このメーカーはまさにそんなスピリッツに溢れていたのだ。
そして翌’66年に、現在の軽自動車王国の基盤とも言える「フェロー」がデビューする。「フェローバギー」は、実用一辺倒の軽自動車カテゴリーにあって、フェローをベースに文字通り遊びのエスプリを最大限に注入したクルマであろう。
当時アメリカではVW(ビートル)をベースにした「バギー」が若者たちの間で大流行していた。その中心的なビルダーは「メイヤーズマンクス」で、VWのシャシー(フレーム構造だったから、カスタマイズは比較的簡単だったらしい)を使って、ワイルドなバギーボディを換装。それを駆ってサーファー(みたいな)が海岸を疾走するシーンは、さすがに保守的な日本ではちょっと先走り過ぎの感はあったが、フレーム構造(今でこそほとんどの乗用車はモノコック構造だが、当時は逆にトラック同様フレーム構造が大半だった)のフェローをベースに、ダイハツはそれを実現させてしまった。
そこには、若者の夢に忠実なダイハツのエスプリが感じ取れる。まるで「クルマに遊びがあって、何が悪い!」と訴えているようでもあった。
残念ながら、フェローバギーは100台の限定だったから、目的が普及ではなかった。’68年の東京モーターショーで参考出品された、「スピード」、「ビーチ」、「カントリー」の3台のうち、その反響の高さに応えて「ビーチ」仕様が市販されたというのが実態だ。
その100台が、どこのどういう人の手に渡ったかはさだかではない。しかし、たった1台当時のダイハツ広報部には存在し、それに触れることが出来たのだ。
とにかく目立って困った!
通常は当時日本橋にあったダイハツ東京支社に広報車両を借りにいくのだが、どういうわけかこのクルマ、渋谷のNHKに取りにいった。なんかの番組に使っていたのだろう。
NHKの大道具施設の外に、赤と白のフェローバギーはあった。存在だけでワクワクするのは、その容姿が遊び目的の一点に割り切られていたからに他ならない。
シートはちゃんとしたビニールレザーだったが、むき出しのフロアも何も外装はすべてFRPだから、自動車という感じがしない。なんてったってドアもないのだから。
借りた時はまだ昼間だったので、照れもあってNHK近くの知人のデザイナー事務所で暗くなるまで時間を稼ぐ。そして、そこからどこをどう走ったかは覚えていないが編集部のある外神田まで夜の都内を走ったことだけは間違いない。
いくら40年近く前のこととはいえ、東京の道路にクルマと人通りは絶えない。走行中も誰ともなく「あれ、何!」とか、「かっこいいじゃんよ〜」といった声が聞こえてくる。聞こえるわけだ、屋根も何もないのだから。
当然、信号待ちを何度も強いられる。今度は近くを通る人たちの声ではないが、好奇の視線をビシビシ感じる。まだ20代の序盤だったからちょっぴり恥ずかしかった反面、妙な優越感も感じていたように覚えている。なんとなくハイな気分だ。
クルマに格別パワーはないけれど、軽いボディとも相まって、その走りは軽快そのもの。もとより操縦性うんぬんを論じるクルマではない。しかし、少なくても都市部を走るクルマとしては、いささか不適当であったことだけは確か。まさに海岸こそが似合うバギーそのものだったのだ。そういう割り切りが出来た時代でもあった。
そんな遊び心に用途を限定したクルマは、フェローバギー以後も国内メーカーから何台かが登場したように記憶するが、この国はそういう遊び心を捨て、機能一手張りでひたすら自動車大国へと進んでいくのであった。
もう、二度とこのようなエスプリはこの国からは生まれないのであろうか。いや、遊び心とは言わないまでも、クルマが画一化されているかに見える現在、まったく違う新たな付加価値は生んでいかねばならない時代だ。
フェローバギーのスピリッツに、そんなヒントが隠されているように思えてならない。
2009.07.14記


こちらもどうぞ!

No.011 自動車メーカー、エスプリの時代Act2 ベレットGTR
いすゞベレットは、’64年のデビューから’73年まで、国産スポーティモデルの代表として君臨していた。スカイラインGTが「スカG」と愛称(略称)で呼ばれたように、ベレットGTは俗称「ベレG」と呼ばれるほどのアイドルぶり、老若を問わずクルマ好きの憧れのクルマであったことは間違いない。「ジーティー」という響きにも人はときめいた時代だ。
ベレットGTRはベレット・シリーズのフラッグシップモデル(当時は、そういう表現はなかったが)で、’69年にデビュー。当時イタリア・ギア社に在籍していた巨匠ジウジアーロがデザインした同社の117クーペに搭載されていたDOHCエンジンを拝借し、他のベレットGTとの差別化を図るため、フォグランプ付きの精悍なマスクだけでなく、専用に強化された足回りを持つ、文字通り超スパルタンなスポーツカーであった。
時系列から鑑みるに、’69年に私はこの業界におらず、どうやら試乗したのはマイナーチェンジを施した’71年であったようだ。当然ながら私の運転技術が未熟な時に、こんな凄いクルマに試乗出来てしまうのだから、この業界(自動車雑誌業界)はこわい。
今も昔もいすゞ自動車本社は大森にある。普通、試乗に供されるクルマ(広報車両と呼ばれる)は、この本社から借り受けるのだが、この時はなぜか目黒にある広報車両のメンテナンスをするディーラーに借りにいった。私一人ではなく編集長(以下:編)といっしょだったことを克明に覚えている。
そちらに伺うと、白衣をまとった初老の紳士が対応してくれた。お名前までは記憶していないが胸の名札には「カードクター」とある。そこで白衣をまとっていることに合点がいった。「この方、クルマのお医者さんなんだ」と。
さらに、「クルマもこのくらいになると、普通のメカニックではなく、えらい人しか触れないのかな」などと、なんの根拠もないバカな想像までしている自分が滑稽だった。
昔、スポーツカーはスパルタンが普通だった
免許歴としては「編」の方が長かったこともあり、最初の運転は「編」に委ねる。そこから目黒通り、環8、東名高速道路(開通してわずか2〜3年)で箱根方面へ。当然助手席に座っていたわけだが、その時の記憶はまったくない。もしかしたら隣でグースカ寝てしまっていたのかもしれない。「編」はやさしい人だから、別に咎めもしなかったのだろう。
そこからの記憶は断片的で恐縮だが、箱根ターンパイクと、当時はまだダートだった長尾峠しか覚えていない。つまり、私がハンドルを握れたのはこの2個所だったのだろう。ともあれ、ついにその時はやってきた。
編:「Hくん、運転してみる?」
私:「は、はい。いいすか? んじゃ遠慮なく。・・・・・(しばらく時間が経過)すんません、これクラッチ壊れてません?」
編:「なんで?」
私:「踏んでも動かないっすよ」
編:「あのね! 重いだけだよ、気合い入れて踏み込まなきゃ。アクセルもブレーキも同じに重いからね」
私:「ほんとですね、凄く重い。でも慣れればなんとかなるもんですね、一時はどうなることかと思いましたけど。フ〜・・・・・」
編:「別に無理して速く走らなくていいんだからね」と、安全運転を促される。
私:「慣れてくると、ついついアクセル踏みたくなっちゃいますね。シフトも超ショートストロークでキマると断然気持ちいい。これがスポーツカーってもんなんですね、ワクワク・・・・・。編さん、ヒール&トウの練習してもいいすか?」
編:「どうぞご勝手に・・・・・、でも無理しなさんなよ」
私:「それじゃあ、お言葉に甘えまして。・・・・・カチ〜ン、いてててててッ!」
編:「どした?」
私:「あの、み、みみみ右足がつっちまいました」
編:「きみ、若いわりには運動不足なんだね。ほんと手間のかかるやっちゃ」
私:「くやしいですっ!(サブングル風)」

No.020 自動車メーカー、エスプリの時代Act4 スバルff-1 1300G
スポーティかつ先進的であることが「売れる条件」だった時代が、’60年代末期から’70年代初頭だったのではないだろうか。
それを象徴するのが「スバルff-1 1300G」だ。トヨタのカローラ、日産のサニーといった強力な大衆車の巨人の中にあって、何か違う付加価値を見出さないと埋もれてしまう時代だ。このクルマの他との最大の違いは「FF方式」だったことだ。えっ!? と思われるかもしれないが、当時唯一無比のFF機構を採用したのは、スバルだったのだ。
てんとう虫の愛称で一世を風靡したスバル360の「RR」に対し、’66年にデビューしたスバル1000(バルセンの愛称を持っていた)はFFだった。それだけではない。独特のスバルサウンドを奏でる水平対向エンジン、フロントのダブルウイッシュボーン・サスペンションも高価な機構だが、ブレーキ本体をドライブシャフトのタイヤ側ではなく、付け根側に設置した「インボードタイプ・ブレーキ」も画期的だった。これはバネ下重量の軽減に貢献している。実にマニアックな設定だったことで、そこら辺の大衆車とはちょっと違いまっせ〜、とアピールしたのだ。*メンテナンスは大変だった。
周りのクルマがどんどん排気量を上げていく傾向だったため、スバル1000も例にもれず、’69年に1100cc(ff-1となる)、’70年には1300ccにスケールアップしていき、いわゆるパワーアップ合戦の真っ只中を歩んでいくことになる。
1300になって、1000や1100ファンの意見は二分した。肯定派はトルクが増して運転がやさしく(楽に)なったことが挙げられている。一方否定派は、エンジンを高回転に保たないと(ピーキーという表現だった)活発に走れない特性が、逆にやさしくなって「走りがつまらなくなった」という意見だ。
昔からスポーツカー(ファンはスバルをそう思っていた)は、エンジンはピーキーで当たり前。誰にでもやさしいクルマでは面白くない、という思想がまことしやかに語られていたのだった。
そんなスポーツカーにスバルが思われていたことは確かなことで、メーカーのエンジニアにとっては名誉なことであったに違いない。
しかし、’71年にシリーズは1400へのスケールアップと同時に、名称は「レオーネ」に変わり、先進メカの塊から、わりと普通のクルマへと変遷を余儀なくされていく。
‘70年7月10日に発売となった1300Gがラインオフするメーカー写真。1000や1100との大きな違いは専用のラジエターグリル。ボディの基本シルエットは共通だ
‘61年の東京モーターショーに出展された「スバル・スポーツ」。スバル450をベースにしたオープン2シーターで、限られた資源の中でスポーツ、走りを目指す当時の富士重工の姿勢やスピリッツが垣間見られる。
スバルff-1の歴史はラリーの歴史
No.009 自動車メーカー、エスプリの時代Act1 ホンダ1300クーペ9
自動車メーカーと自動車は、往時はどんな輝き方をしていたのだろうか、という視点で私がとことん若かった’70年代、つまり私自身もバカなりに夢と希望に燃えていた時代を中心に、メーカーが良い意味で遊び心満載であった頃のクルマを回想します。
「売れなければ、いい商品ではない」という現在の価値観を根底から覆す、意欲とエスプリとアイデアに溢れていた時代を、単なる懐かしさだけで回想するのではなく、冒険や挑戦を恐れない当時の経営者や商品企画者、エンジニアたちの熱い思いが、今でも通用する何かを感じ取っていただければうれしく思います。
紹介するクルマは、私が実際に触って、乗ったクルマです。挿入のイラストは友人の古岡修一画伯のご厚意で、快くご提供していただきました。
ホンダ1300は、’69年にセダン、’70年にクーペが発表されている(メーカーの系図参照)。
1キャブレター仕様と4キャブレター仕様があり、前者の呼称はセダンが「77」、クーペが「7」、後者は「99」と「9」と呼ばれていた。
1300のスペックを超えた、ホンダの意地
意欲的なボディシルエットは、イラストや写真を見ていただくとして、まず、当時のニュースリリースを覗いてみよう。