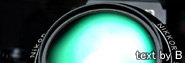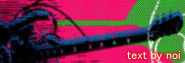スポーティかつ先進的であることが「売れる条件」だった時代が、’60年代末期から’70年代初頭だったのではないだろうか。
それを象徴するのが「スバルff-1 1300G」だ。トヨタのカローラ、日産のサニーといった強力な大衆車の巨人の中にあって、何か違う付加価値を見出さないと埋もれてしまう時代だ。このクルマの他との最大の違いは「FF方式」だったことだ。えっ!? と思われるかもしれないが、当時唯一無比のFF機構を採用したのは、スバルだったのだ。
てんとう虫の愛称で一世を風靡したスバル360の「RR」に対し、’66年にデビューしたスバル1000(バルセンの愛称を持っていた)はFFだった。それだけではない。独特のスバルサウンドを奏でる水平対向エンジン、フロントのダブルウイッシュボーン・サスペンションも高価な機構だが、ブレーキ本体をドライブシャフトのタイヤ側ではなく、付け根側に設置した「インボードタイプ・ブレーキ」も画期的だった。これはバネ下重量の軽減に貢献している。実にマニアックな設定だったことで、そこら辺の大衆車とはちょっと違いまっせ〜、とアピールしたのだ。*メンテナンスは大変だった。
周りのクルマがどんどん排気量を上げていく傾向だったため、スバル1000も例にもれず、’69年に1100cc(ff-1となる)、’70年には1300ccにスケールアップしていき、いわゆるパワーアップ合戦の真っ只中を歩んでいくことになる。
1300になって、1000や1100ファンの意見は二分した。肯定派はトルクが増して運転がやさしく(楽に)なったことが挙げられている。一方否定派は、エンジンを高回転に保たないと(ピーキーという表現だった)活発に走れない特性が、逆にやさしくなって「走りがつまらなくなった」という意見だ。
昔からスポーツカー(ファンはスバルをそう思っていた)は、エンジンはピーキーで当たり前。誰にでもやさしいクルマでは面白くない、という思想がまことしやかに語られていたのだった。
そんなスポーツカーにスバルが思われていたことは確かなことで、メーカーのエンジニアにとっては名誉なことであったに違いない。
しかし、’71年にシリーズは1400へのスケールアップと同時に、名称は「レオーネ」に変わり、先進メカの塊から、わりと普通のクルマへと変遷を余儀なくされていく。
 ‘70年7月10日に発売となった1300Gがラインオフするメーカー写真。1000や1100との大きな違いは専用のラジエターグリル。ボディの基本シルエットは共通だ |
 ‘61年の東京モーターショーに出展された「スバル・スポーツ」。スバル450をベースにしたオープン2シーターで、限られた資源の中でスポーツ、走りを目指す当時の富士重工の姿勢やスピリッツが垣間見られる。 |
スバルff-1の歴史はラリーの歴史
1300Gの思い出を語る上で、絶対にはずせないのがラリー活動だ。
今と違って未舗装路(ダート)が豊富にあった時代。変な言い方だが、当時のクルマの条件として悪路の走破能力が、性能を語る上で重要なファクターになっていたのだ。それほど、日本の道路はオソマツだった(蛇足だが、現在道路にお金を掛け続けるのは、そのころの反動なのかも!?)。
スバル(富士重工)の本社は新宿西口にあるが、製造の本拠地は上州(群馬県)だ。その、良くも悪くも泥臭い精神がスバルには宿っていたのは事実。山道に強いのだ。
1300のポテンシャルを示す最大のアピールの場が国内ラリー活動だった。岩下良雄、横山文一、小関典幸、高岡祥郎が当時ドライバーの看板。岩下、横山は契約の立場で、小関はスバルの実験部、高岡はこれを機にスバルの社員になっている。
ラリーをやっていた人も、ただ見ていた人も、「TEAM SUBARU」とマーキングされたワークス仕様の1300Gに魅了された。現在のような派手なスポンサー・カラーもないのにもかかわらずだ。その実績と実力もさることながら、独特のサウンドで山道を疾走する姿に圧倒されたのだ。もちろんスバル1000の時代から日本アルペンラリーなどで輝かしい戦績を残していることは言うまでもない。
ラリー活動を企業の宣伝活動だけと考えるのは、ちょっと勘違いだ。実は壮大な実験活動の場でもある。通常、メーカーには実験部があって日々クルマをチェック、開発している。ラリーは短時間にして場合によってはクルマに1年分以上のストレスを与える競技だ。つまり、限られた時間内に膨大なデータが収集できる。短い時間でクルマの弱点や気付かなかった部分が発見でき、個体に適宜フィードバックするきっかけとなる。
モータースポーツ活動を決してあなどってはならない。コンピューター解析全盛の今はどうか分からないが・・・・。
私が所属していた媒体は「非舗装路専門誌」(そんなのあったの!)であった関係上、クルマの試乗もダートの山道、それも夜中が多かった。スバル1300Gの時もその例にもれなかったと記憶している。
カタログ上のパワーは93馬力/7000回転(高い!)と、一見大したことなさそうだが、その加速の鋭さは思わず唸りたくなるような元気ぶりだ。例外的に元気が良かったカローラ・レビン/スプリンター・トレノ(TE27型)デビューの2年前ということもあり、おそらくこの1300Gがクラス最高の元気さを誇っていたのではないだろうか。
次にハンドリング。操向と駆動を一手に担う前輪は実に大人。操舵時に多めのパワーをかければ順当にアンダーステアが増し、アクセルオフすれば思ったとおりのタックイン現象(内側に切れ込む)が起きる。それは急激ではなく、いたって穏やかだ。それらはハンドルを伝ってドライバーにちゃんと教えてくれるのだ。
見たところタイヤも細い(カタログ上は145SR13)し、奇をてらった部分は微塵もない。そこが大人だ。
当時、本当のクルマ好き(エンスーやマニアともちょっと違う)が1300Gのとりこになった理由は、一にも二にも「その大人っぷりとエスプリ」にではないだろうか。今でもそう確信している。スバルにはクルマが持つべき基本と本来が凝縮されている、とも思う。
2009.06.09記